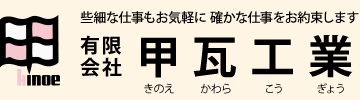屋根雪
今年は突然の大雪で、みんなびっくり。僕たちも、雪下ろしの依頼がたくさんあって、作業させて頂きました。訪問が遅れたお客様には、大変申し訳ありませんでした。
少し落ち着いてきたと思ったら、「軒先が折れてしまった」という相談がチラホラ・・・そこで、今回は、屋根雪についてお話したいと思います。

軒先が折れる事例の傾向として、雪止め瓦を施工していない案件が増えています。
理由として、北陸地方の湿った雪質に加え、一度に多くの雪が積もる「ドカ雪」が増え、今まで、日中など温かくなった時に落ちていた屋根雪が、落ちずに残ってしまうといった理由があります。

建物の構造材の内、軒先部分の部材を「軒桁(のきけた)」と呼んでいます。
屋根雪では「軒桁」より先に掛かる負荷を考える必要があります。

屋根雪は1m四方(1㎥)で、新雪時では約50㎏だった雪が、湿った状態では10倍の約500㎏まで重くなります。屋根雪が融けて、見た目は少なくなったように見えても、危険性は、むしろ増加しています。
「屋根雪が融けた」という理由で、雪下ろし作業をキャンセルされるお客様がおられますが、安心するのは間違いです。

写真は、雪止め瓦を入れていない屋根です。
軒先で、屋根雪が巻くような状態になり軒先に大きな負荷がかかります。
瓦が新しく、表面に艶がある時は良く落ちますが、古くなると、落ちにくくなっていきます。

屋根の高い部分より、軒先の方が積雪が多いことがわかります。

雪止め瓦を入れた状態でも、荷重で割れてしまう事があり、軒先部分に被害が集中する事が多いです。

「雪止め瓦」を施工していても大雪で放置していると折れてしまいます。
軒先が折れた際の対応については、実績11「雪害対応 瓦葺き直し工事」で、紹介しています。

軒先高さが低い場合は、軒下にたまった雪と屋根雪が一体となって、軒先に負荷をかける事が想定されます。
この案件では、下地を支える「垂木(たるき)」と呼んでいる角材を新調し、雪止め瓦を施工して「軒先」と「軒下」がしっかりと離れる様に工夫しました。

軒先と積雪がつながると、大きな負荷がかかるので、雪下ろしの際などは必ず離れるようにします。

経年劣化により、瓦を緊結する「桟木」が、折れてしまう事もよくあります。
定期的な点検とメンテナンスに加えて、屋根雪が積もり過ぎないようにする事が大切です。
「雪が融けにくい形状や方角」「下屋根で上に屋根がある」ような条件の場合は要注意です。

写真は、雪止め瓦を施工した案件です。
冬季では「雪止め瓦」を葺いていない屋根での
「雪下ろし作業」
「屋根に登っての点検作業」「修理作業」等は
「大変危険なので基本的にお断りしています」。
該当する案件については、降雪前に屋根の対応を済ませておくことをお勧めします。
「雪止め瓦」には、枝葉が溜まるなどのデメリットもありますが、今一度、再考して頂くのも良いかと思います。