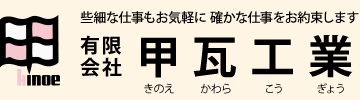お寺 鬼瓦取り付け
「軒棟」の下地が完成して、いよいよ鬼瓦を取り付けます。鬼瓦は、冬の間から準備をしてきた、取り返しがつかない瓦です。一番目立つ部分なので、慎重に作業を進めます。

初めに「抱きがね」と呼んでいる鬼瓦を支える金具を「下がり丸」の頂部に取り付けます。

こだわりは、双方の部材の接続部分である「合掌」です。漆喰やコーキングは、便利ですが瓦ほど長持ちせず、見た目にも美しくありません。以上の理由から、弊社では、目に見える部位はできるだけ「瓦」を使用する事にこだわっています。「鬼瓦」と「下地を含めた合掌」が一体となって初めて美しい屋根ができると考えています。
「お寺」の屋根を見る機会があればぜひ注目して頂きたい部位です!
「抱きがね」については、鬼瓦を実寸してから制作する事により、実物に合った寸法や角度を求め、瓦の加工も併せて美しい仕上がりを目指しました。

「鬼瓦」は、5つのパーツに分かれていて、各パーツをステンレス線で緊結します。前もって、緊結線を鬼瓦に通しておきます。通す部位が、狭いので時間と労力を要します。

「下部のパーツ」を「抱きがね」に載せて仮に緊結します。

前後左右から確認を繰り返し、ベストポジションを探します。

あらかた定まった所で「束」と「鬼瓦」を仮に緊結します。

弊社では「頭」と呼んでいる上部のパーツを差し込みます。

瓦は「焼き物」です。ねじれや傾きがあって当たり前です。工夫して、調整を重ねます。

「頭」の位置も定まったら、仮の緊結を締め直し「つっかえ棒」をして、鬼瓦の取り付けは完工です。

緊結部分です。「不完全な形状を美しく組み立てる」作業でした。

目に見えない部分には「シール」を有効に活用します。

ここからは取り返しのつかない作業が続きます。一切の妥協を許さず、悔いのない作業を進めています。