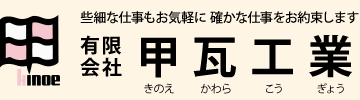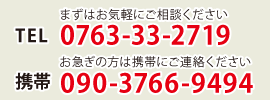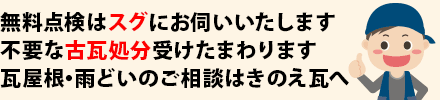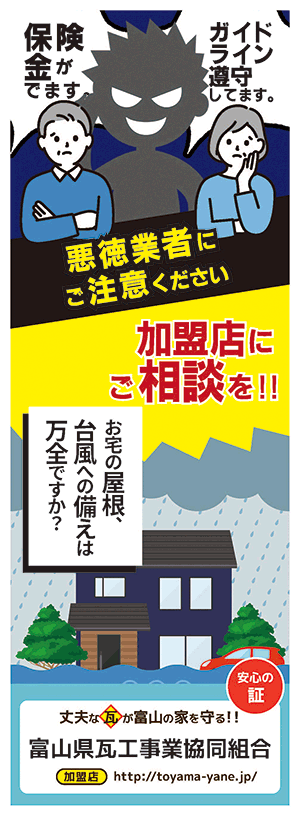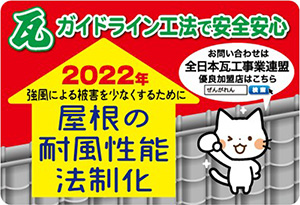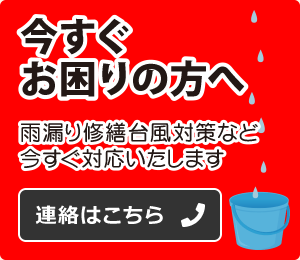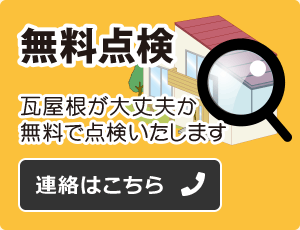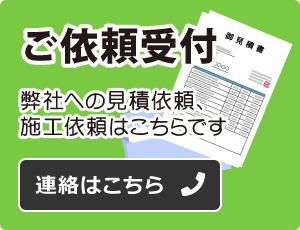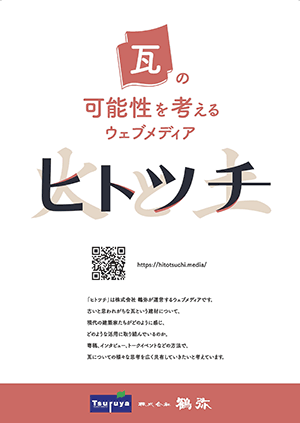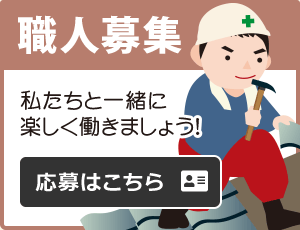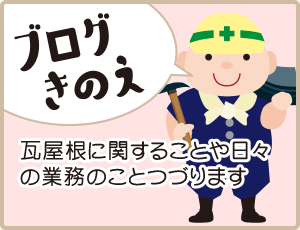⑲「強力棟」の「芯木」交換工事

「棟部」を「冠瓦」のみで仕上げる工法を「強力棟工法」と呼んでいます。「瓦葺き部」は「平板瓦・F型」と呼んでいる仕様で、屋根材は色や型式の廃番等も考えられるので、ある程度ストックを確保しておくことをお勧めします。
強風で「冠瓦」が欠落する被害がありました。「冠瓦」を緊結する「芯木」の腐食が原因と判断し「芯木」の交換作業を施工しました。施工不良や欠陥によって被害が起こる事は少なく、ほとんどが想定の範囲内のメンテナンス工事と言えます。メンテナンス作業では、使用する部材によって仕上がりが大きく変わるので、妥協はしません!

「強力棟工法」は、内部にある「芯木」に「冠瓦」を「ビス」や「釘」で緊結する工法です。年数を経て「芯木」が劣化すると、強風等で「冠瓦」が欠落する恐れがあります。「芯木」には開口をふさぐための「棟土」が施工してあり「湿式・しっしき」と呼んでいます。

「冠瓦」を緊結する「芯木」がしっかりしていないと緊結の効果がありません。写真の案件では「釘」で緊結してあり、強風の負荷により、少しずつ釘が浮いて、緩みが大きくなっていく事が想像できます。欠落した場合、二次災害の恐れもあるので要注意です。

「芯木」は内部にあるので、気付きにくい部位です。知らずに、内部の棟土も流失していきます。

対応として「棟部」を解体して「芯木」を交換します。「棟部」を支える土台となる部位のメンテナンスも同時に行います。ズレや勾配を適切に直し、開口の隙間が大きい時は切り直します。廃番になっている場合は、代替品を探す必要があります。

弊社では「棟土」を使用しない「乾式・かんしき」と呼んでいる仕様を採用しています。「シール」で防水を確保し「芯木」を腐食しにくい「人口樹脂製」に交換した上で、より緊結力が強い専用のビスで「冠瓦」を固定します。写真は「冠瓦」の表面に「目地」を覆う「紐(ひも)」と呼ばれる「突起状のカバー」がある仕様です

「棟土」は劣化による流失が進んだ場合、下地が露出してしまう事があるので、定期的な点検と適切なメンテナンスが大切になります。写真は「冠瓦」の表面に「紐」が無い仕様です。

対応工事では、オレンジ色で示した「人口樹脂製の芯木」を緑色で示した「棟金具」黄色で示した「ジョイント金具」で固定して、赤色で示した「シール」で防水を確保します。メンテナンス工事では「冠瓦」は「再使用」できますが既に廃版となっている場合は今後を考えて交換する事も相談させて頂いています。

「棟部」は他の部位と比べて、風圧力が大きくアンテナの緊結線の結束など、本来の用途とは違う使い方も見られる事から、定期的な点検とメンテナンスが必要です。作業の前後で、どこが改善されたのか分かりにくい工事ですが、安心して暮らして頂くためには大切な工事です。